家族と話し合うべき「空き家の相続」チェックリスト【2025年版・静岡編】
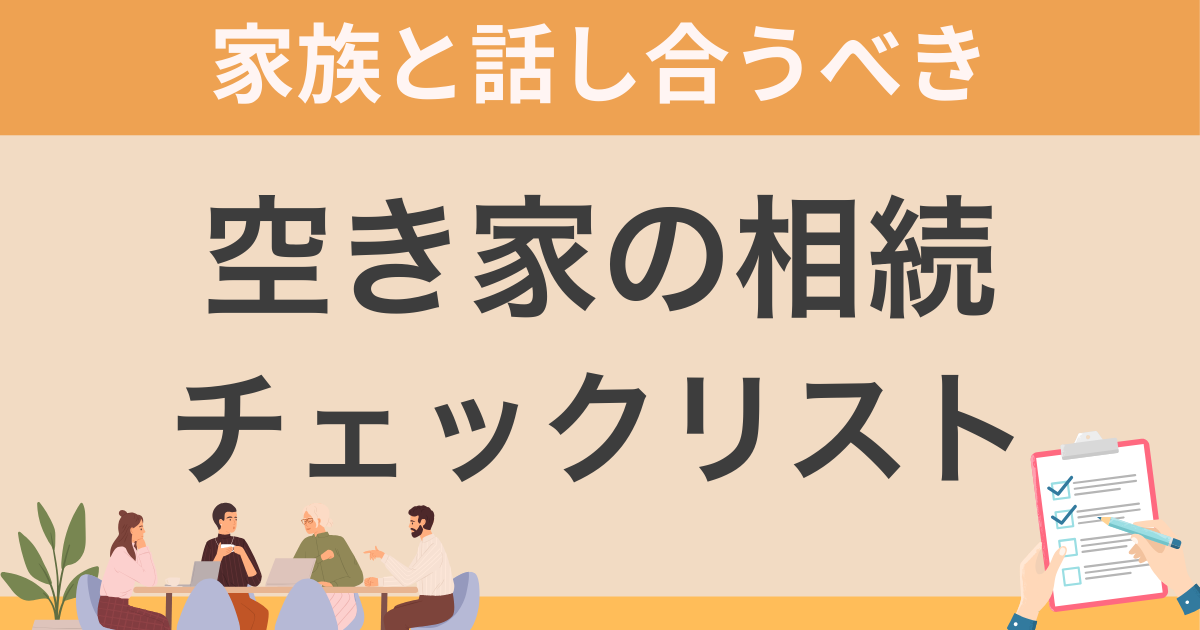
静岡県の空き家は相続の問題が原因?
みなさんは家族と「空き家の相続」について
話し合っていますか?
家族全体で話し合いを
しておくことが、将来的な争いや金銭的損失を
防ぐカギになります。
特に、近年は全国的に空き家の
増加が深刻な問題となっており、静岡県も例外ではありません。
総務省の調査によると、2023年時点で
静岡県内の空き家数は約29万戸。
これは県内の住宅全体の約16%を占め、
全国平均(13.8%)を上回る水準です。
(出典:総務省 住宅・土地統計調査 2023年)
特に中山間地域では相続未登記の空き家や
管理が行き届かない家屋が目立ち、
防災・衛生の観点からも社会問題化しています。
この記事では空き家の相続において
家族で話し合うべきポイントを
「チェックリスト形式」で紹介し、
どのような準備や確認をしておくべきかを解説します。

なぜ今、空き家の相続が問題なのか?
相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年から「相続登記の義務化」がスタート。
相続により不動産を取得した場合、
取得を知った日から3年以内に登記を
行わなければ10万円以下の過料が
科される可能性があります。
これは「所有者不明の土地・建物」を
減らすための対策ですが、
逆に言えば相続放置が
リスクになる時代になったとも言えます。
家族と確認すべき
「空き家相続チェックリスト」
以下のチェックリストをもとに、
家族内で空き家についての状況を共有しましょう。
✅ 1. 空き家の所在地と現況を知っているか
- どこにあるのか?
- 土地の境界線は明確になっているのか
- どのくらい使っていないのか?
- 現在の状態は?(雨漏り・傾き・
庭の荒れなど)
※写真やGoogleマップでの確認だけでも効果的。
✅ 2. 相続関係と所有権を把握しているか
- 被相続人は誰か?
- 相続人は何人か?
- 現在の登記名義人は誰か?
- 遺言書の有無は?
法務局で登記事項証明書を取得すると、
名義人の確認が可能です。
(インターネットでも取得可能)
✅ 3. 相続の意思と方向性があるか
- 売却するのか、活用するのか、解体するのか?
- 相続放棄の検討は?
- 遺産分割協議が進んでいるか?
(遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、
合意するための協議のこと。合意が成立すると「遺産分割協議書」を作成します)
明確に結論を出せなくても、
家族で「方向性を共有する」だけでも
後々の争いやトラブルを防ぐことができます。
✅ 4. 税金・維持費がいくらかかっているか
- 固定資産税の金額
- 空き家管理費(業者委託含む)
- 解体費用の概算
(木造の場合200万〜300万円前後)
空き家は管理不全空き家や特定空き家に指定されると、住宅用地特例(税額6分の1)が解除され、
固定資産税が最大6倍になるケースもあります。
✅ 5. 利用や売却の可能性を検討しているか
- 空き家バンクへの登録予定の有無
(空き家バンクとは、自治体などが空き家の所有者と利用希望者をマッチングするために設置している制度) - 利用希望者がいないか(親戚・近隣など)
- 立地条件や市場価値の調査は済んでいるか
最近では、静岡市や浜松市などでも移住者向けに空き家を活用する自治体施策が充実しており、
売却・活用の可能性も拡大しています。
静岡の事例に見る
「空き家放置」のリスク
ケース1:老朽化空き家の一部崩落により近隣住民が通報
静岡県中部のある市では、長年放置されていた空き家の瓦が落下し、
近隣住民から通報が相次ぎました。
市は所有者に改善を指導しましたが、連絡が取れず、
「特定空き家」指定により行政代執行による解体を検討する事態に。
→ 適切な相続・登記が行われていれば防げた可能性も
まとめ|今だからこそ、家族で未来の空き家を考える
空き家は放置すればするほど
「管理コスト」と「リスク」が膨らみます。
特に相続人同士の関係が希薄になる前に、
家族全体で話し合いをしておくことが、
将来的な争いや金銭的損失を防ぐカギとなります。
✔ 家族が集まるときは相続の話をするチャンス
- 実家の空き家、誰が相続する?
- 活用か、売却か、放棄か。
- 登記や税金、いくらかかるのか?
気まずさを恐れず、
「今だからこそ」話しておきましょう。
\静岡の空き家でお困りであればまずは無料でご相談下さい!/
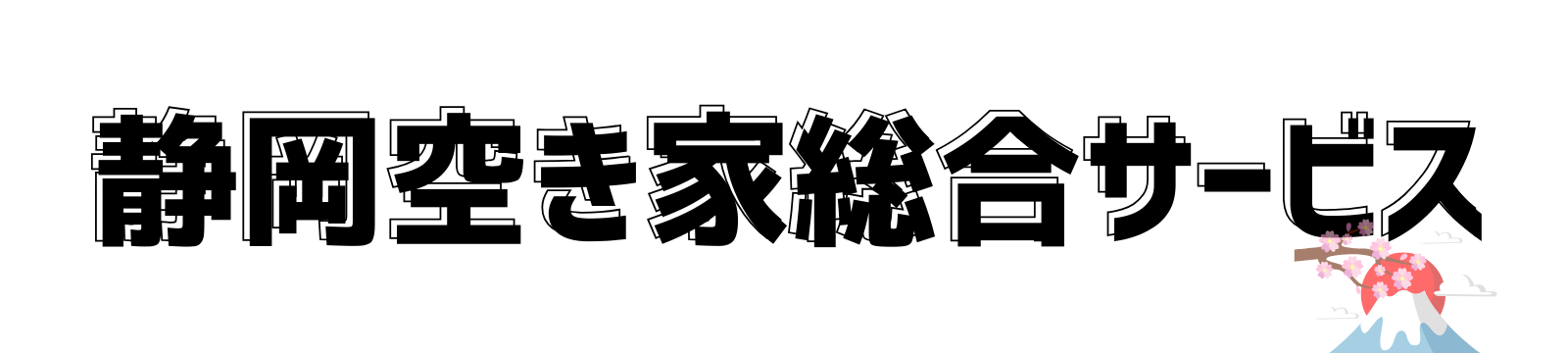
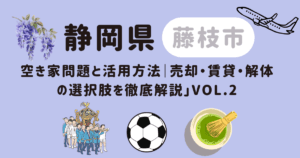
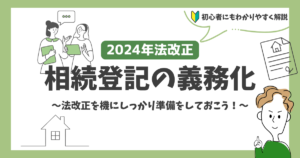
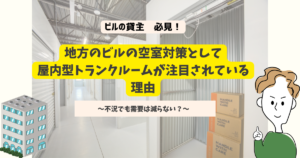

コメント